こんにちは、音葉です。
暗譜といえば、なんだか難しいイメージを持っていたり、記憶力がたくさん必要なのかなと思われている方もいらっしゃると思います。
また、普段は暗譜していなくて、発表会やコンクールのみ暗譜をしていて、それっていいの?と疑問に思っている方もいらっしゃると思います。
今回は、ピアノや他の楽器を習っている方なら、誰もが悩んでいる暗譜について考えていきたいと思います。

・ピアノの暗譜はどうすればいい?
・いつ暗譜するのがいい?

暗譜をするタイミングやその方法
みなさんは、どのタイミングで暗譜を始めますか?
私は、一通り曲の最後までレッスンが終わって、いろいろ訂正を加えたあたりから、暗譜を始めます。
曲によっては、譜読みに時間がかかってしまって、なんとか弾けるようになった頃には同時に暗譜も終わっている曲があります。
いろいろなピアノの先生の意見を参考にしながら、1番いい方法を考えていきます。
引用:https://www.piano-k.net/article/kikaku_2208_qa_00066.html
練習と暗譜を同時進行で行うと、読み間違いが多くなりやすいのでオススメできません。
また、強弱などの表現にまで目がいくようになってから暗譜する方が、より高いレベルで曲を仕上げられると思います。
一度暗譜をすると、楽譜の細部まで気をつけてみながら弾くという機会が少なくなると思います。
少なくとも私は、暗譜してしまうと、楽譜をあまり見ずに弾いてしまうため、音の間違いやリズムに気がつかずにレッスンに行ってしまうこともありました。
そのため、できるだけ正確に弾けるようになってから暗譜をすると、このようなことは防げるのではないかと思います。
その一方で、このような意見もありました。
暗譜するぞ~!と思わなくても、部分練習をすれば細かい音や指使いの暗譜が自然にできてくるかと思います。
ただ、大人ピアノは、分析をしっかりされるといいですね。
intro-A-B-A-codaの形式だな~
こことここは同じ。
1回目のAと2回目のAはこのリズムが違う。この音から変化する。などなど…
漫然と最初から通すのではなく、気づいたことを言語化しながら練習すると、練習効率も上がりますし、かなり暗譜の助けになります。楽譜なしで弾けるようになってからも、楽譜を見て練習するといろいろ気づくこともありますね。
子どもの頃は、ただがむしゃらに覚えていた方もいらっしゃると思います。
私もそうでした、最近でもそうかもしれませんが・・・
しかし、大人の方は、暗譜をするために曲の分析をしたり、脳を使いながら覚えるのもいい練習になると思います。
また、楽典知識をせっかく習ったのであれば、その知識を生かすこともできます!
私は、モーツァルトのピアノソナタ18番を暗譜した際、先生に分析!とよく言われていました。
何度も転調したり、どんどん転調していく曲は、暗譜がとても難しいです。
また、ピアノソナタのように、またもとに戻ってしまう(再現部)のある曲を暗譜すると、気がつけば最初に戻っていた!ということもありえます。
暗譜をした後も、頭の中に分析が残っていればそのようなことも防げるはずです。
本当に暗譜が苦手な方は、
楽譜を書き写したりして覚える方もいらっしゃいます。
また片手ずつ暗譜などもしてみてもよいかと思います。
とくに左手など伴奏部分は何気なく弾いてしまっていることも多いので、
しっかり覚えることにより、ベースの表情などが感じられ、
曲の仕上がりが立体的になりますよ。
私も、少しだけ楽譜を書き写したことがあります。
どうしても覚えられない!という箇所のみ、楽譜を書き写しました。
すると、左と右のハーモニーについて新たに気づくことがあり、曲への理解が深まったり、ここは特に気をつけて左の音を聞う!といった発見がありました。


普段から暗譜は必要?
発表会前に、暗譜に苦戦するのは、普段から暗譜の習慣ができていないからではないか、と思いました。
もしかすると、それも原因の1つかもしれませんんが、無理に弾く曲全てを暗譜する必要はないと考えられます。
殊更に暗譜しようと思わなくても、譜面を見ながら何度も練習しているうちに自然に覚えてしまうのがいちばん良いと思っています。それだけ身についたと言えるからです。
逆に覚えにくい曲は無理に覚えなくても完成させることはできますし、必ずしも1曲1曲全部暗譜しなくても、曲によっては暗譜なしで終わらせて、その分幅広くいろいろな曲に挑戦するやり方もあると思います。
暗譜がなかなかできないからといって、同じ曲を暗譜できるまで弾き続けるよりは、せっかくなら他の時代の曲やジャンルの曲にチャレンジするのがいいと思います。

まとめ
今回は、ピアノを暗譜するタイミングとその方法について考えていきました。
2何度も弾いているうちに弾けるようになる場合もあれば、なかなか覚えれない場合もある。その覚えられない部分だけ、楽譜を写してみるのもおすすめ
3発表会やコンクールなど暗譜が義務付けられていない曲は、無理やり暗譜をする必要はない
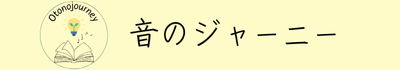

コメント